医薬・電力など社会貢献度の高いシステムを開発。 働く制度を社員が作り、 自ら環境を整備していく
<カイシャの特徴>
●事業内容:社会に貢献 できるシステムを開発
●仕事のやりがい: 複数のプロジェクトに参加可能
●働く環境: 育児中や介護中でも柔軟に働ける
●育成制度:年次ごとの きめ細かい研修制度
医薬・電力・ビジネス情報、三つの分野で社会インフラを支えるシステムを開発
応用ソフト開発は、1984年の設立以来、ソフトウェアの提案、設計、運用、管理を一貫体制で手掛けてきた。確かな実績をもとに、現在は医薬・電力・ビジネス情報の三つの分野を中心としたシステムを受託開発している。医薬システム開発分野では製薬会社を顧客に、希少疾病用医薬品*の治験に関するデータベースの構築や集計分析、さらに実際に薬が販売されてからの市販直後調査として、臨床での検査値などのデータを統計解析している。
電力分野では、電力会社等を顧客に日々の電気使用量予測や、オンラインでの発電制御システムの開発・保守などを行う。
「 医薬分野は希少疾患の患者さんを救う一助を担い、電力分野では電気の安定的な供給支援を担っています。いずれも、システムの受託開発を通して見えないところで社会のインフラを守る事業を行っています」(筒井社長)
もう一つ、ビジネス情報の開発分野は、様々な業界の企業の基幹業務のデジタル化やDX化を手掛けている。
「3分野ともお客様からの要望を形にするだけではなく、まずヒアリングをしっかり行い、当社ならではのプラスαの提案を加えて、要望以上の効果を上げられるように心掛けています」(筒井社長)
今後はクラウドでのシステム提供を進め、同時にLinuxを中心としたオープンソースを今以上に活用し、顧客の費用負担の軽減にも取り組んでいく予定だという。
*希少疾病用医薬品:対象患者数が我が国において5万人未満等の条件に合致する医薬品

横断的に参加できるプロジェクトや委員会で、やりがいを実感
同社には部署がなく、 社員は医薬・電力・ビジネス情報のいずれかのプロジェクトに参加する。ただ、ほかの分野でリソースが不足しているときや、「あの仕事にも関わってみたい」という意欲があれば複数のプロジェクトに参加することもでき、案件を通して様々なスキルを習得することが可能。
また「広報委員会」(SNSなどで会社の広報を担う)、「教育委員会」(社員研修を考える)、「防災委員会」(事業継続計画の策定などを行う)があり、会社全体の方向性を全社員で作り上げている。
「広報委員会の委員長を務めています。委員会では月1回開催する事業戦略会議で、活動の進捗(しんちょく)を確認して、全体の進行を管理するなどの役割を担っています。苦労もありますが裁量も大きく、やりがいを感じています」(入社3年目、ITサービス事業部の原さん)

子育て中など社員一人ひとりの事情に合わせた柔軟な働き方が可能
同社では、 働き方を社員自らが提案できるよう、年に1回就業規則や賃金規定などを全社員で見直している。これまでに、子育て中の社員や家族の介護をしている社員が生き生きと働き続けられるように、在宅勤務制度や短時間勤務制度などを導入してきた。
入社6年目、ITサービス事業部の森本さんは、現在、基本的に在宅勤務で開発業務に携わり、育児の状況に合わせて、勤務時間や業務量を他メンバーと調整しながら業務を進めている。
「面接で結婚後も長く働きたいと話した上で当社に入社しました。ライフステージの変化がある女性も柔軟に働き続けられる職場です」
また、対象者一人当たり年間5日間まで使用できる、子の看護休暇・介護休暇は、同社においては有給で利用実績もあるという。

年次ごとに設定された研修や、財務諸表の読み方を学ぶ会計研修を実施
入社後は社内での新人研修後、チームでプログラムを作成する技術基礎研修を外部で3カ月受講する。その後はメンターの指導のもと、参加するプロジェクトの業務をOJTで習得していく。 以降も2・3年目、4・5年目、6年目以降と年次ごとに技術研修が設定されている。また、社員が会社の経営状態を把握し事業に参加する意識を高めるために、6年目からは自社の財務諸表を読むための会計研修も行う。
さらに、ユニークなのが毎月1回開催されるビジネス書を使っての勉強会。グループに分かれ、本の内容から感じたこと、考えたことを話し合う。
「本自体もいろいろな場面で役立つのですが、ほかの社員の物事の捉え方を知ることができて学びがある勉強会です」(森本さん)

社長からのメッセージ
会社名で選ぶのではなく、やりたい仕事から会社を探してみてください。無理だと諦めず探せば、必ずあなたの夢をかなえる会社と出会えます。

このカイシャが10秒でわかるムービー
ムービーはこちら
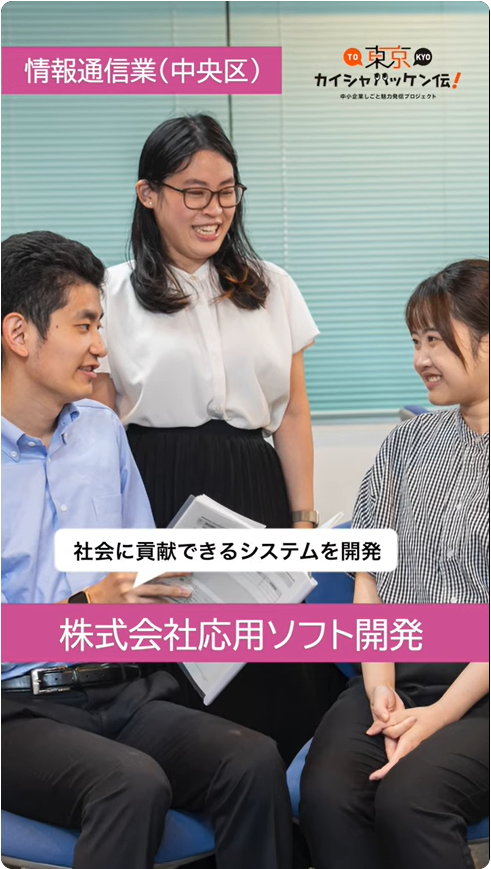
●第39号 (2024年12月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。


