建築と不動産の2本柱で事業を推進。安定した環境で知識・技術を学び続ける
<カイシャの特徴>
●事業内容:建築請負をメインに不動産事業も展開し、安定性と収益性を実現
●育成制度:2カ月の新入社員研修。充実の勉強会や講習会、資格取得も推奨
●働く環境:業務効率化で、残業時間の削減を実現。独身寮は月2,500円
今まで培ってきた実績と 時代を先読みする着眼で 顧客満足をカタチに
首都圏を地盤に約70年の歴史を持つ田中土建工業は、オフィスビルや賃貸マンションなどの自社物件や、官公庁工事などの建築請負事業を中心に実績を築いてきた建設会社。
同社は新築はもちろんのこと、リノベーションやリフォームにも力を入れている。そこには、時代の流れを先読みしながら、顧客のためになる仕事をしようという方針がある。
「少子高齢化で人口が減る中、新築案件に限定せず、お客様のためになる最適な提案をしていくことが、総合建設会社である私たちの役目だと考えています」(入社4年目、採用担当の河面(かわも)さん)
そんな同社では、老人ホームやデイケア施設などの介護関連施設や、待機児童問題が課題になっている都心部での保育園・幼稚園などの施工実績を増やすべくまい進している。
また、建築事業だけでなく、自社物件を賃貸する不動産事業を展開することでも収益を上げている。2つのしっかりとした事業基盤を持つ同社は、安定性と収益性という強みを持ち、設立以来成長を続けているという。
顧客満足を第一に考えた提案を行うという同社のポリシーについて、「建物は建てて終わりではなく、建てる前はもちろん、建てた後からお客様との深いお付き合いが始まると考えています」と話す河面さん。
そうした考えを象徴する一つが責任施工。同社が建設する建物は、全て正社員が責任を持って施工し、納期やコストを相談しながら、安心と安全、そして満足を提供していく。さらに、修繕や定期的なメンテンナンスをはじめ、緊急事態があった際にはスタッフがすぐに駆け付けるアフターサービスにも力を入れているという。
また、耐震の診断や補強、環境負荷の削減と快適性の向上や、建物の長寿命化を考えた省エネ対策を行うなど、全社で持続可能な社会の実現を考えて事業を推進している。

先輩の指導のもとで学び 充実した研修や勉強会で 早く確実に成長できる
同社は、高い技術を早く習得できる育成環境を目指している。新入社員は座学と現場見学を中心に、2カ月かけて道具の使い方などの基礎を学ぶ。配属後は先輩社員の指導を受けつつ、サポート業務を通して、現場に慣れていく。
その他、定期的に勉強会や講習会が開催される。特に講習会は、社員が講師となって習熟度ごとにクラス分けをし、レベルに合った講習を行っている。
入社7年目、工事部工事課で現場次席を務める中尾さんは、講習会で講師も担当しており、「一人ひとり理解度が違うので、伝わりやすい指導を心掛けています」と話す。
また、建設業においては職務と資格が密接に関わるため、同社は資格取得も奨励。一級建築士を取得した若手社員もおり、特定の資格を取得した社員には祝金とともに毎月の手当を支給している。
中尾さんは昨年、一級建築士を取得。「お客様や周囲の評価も上がりますし、自信にもなります」と説明する。
入社3年目、工事部工事課の玉田さんも、現在一級建築士の資格取得を目指して勉強中という。
「入社4年目になる来年には、3年以上の実務経験が必要な1級建築施工管理技士も目指すつもりです」
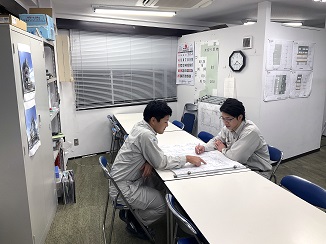

残業削減や有休取得奨励、自社物件の独身寮など、働く環境整備にも注力
設立以来、安定経営を続けている同社は、社員の生活の安定にも力を入れている。例えば、残業時間を削減するために現場向けのアプリを導入し、様々な情報を一括管理、タブレットで確認できるようにした。
「今までは、現場で撮影した写真の整理に時間を取られていましたが、アプリ導入以降、写真が自動的に分類されるようになるなどとても効率的になりました」(玉田さん)
また、飛び石連休や工事と工事の間などに有給休暇取得を推奨するなど、休暇を取りやすくしている。
「学生時代にボクシングをやっていたこともあり、週末はジムで汗を流し、長期休暇は帰省するなどしてリフレッシュしています」(中尾さん)
さらに、30歳までは月額2,500円で独身寮への入居が可能で、ほとんどの新入社員が利用している。
「自社物件の賃貸マンションでプライベートの時間も確保でき、とても快適な住み心地です」(玉田さん)

採用担当からのメッセージ
安定した環境の中で、建築の知識や技術を早くしっかりと身に付けたい人には、最適な職場だと思います。

読者からひとこと
安定した環境で安全な建物を届ける
時代のニーズに合わせた事業を展開する着眼点が素晴らしいと思いました。一番魅力に感じたのは安価な独身寮がある点。自社物件で安心して生活をすることができそうです。また、社内でも互いを高め合いながら働くことができそうと思いました。

●第31号 (2022年12月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。


