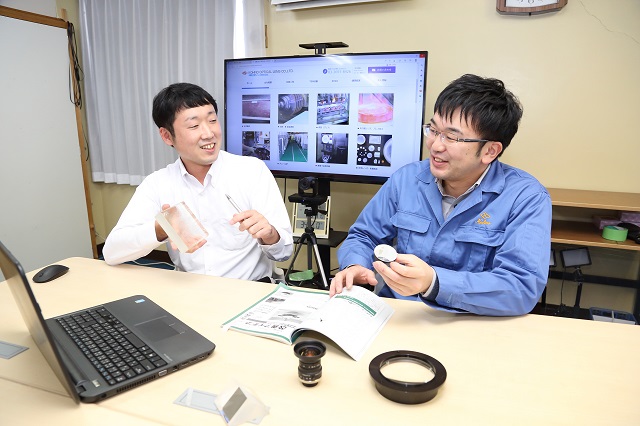若手に技術を継承。一貫生産体制を強みに、高品質な光学レンズを製造する
<カイシャの特徴>
●事業内容:高品質な光学レンズで医療分野や産業分野の「見る」機能を支える
●育成制度:インストラクター制度や若手への技術継承など教える文化が定着
●働く環境:残業が少なく有休も取得しやすい環境。健康経営にも注力
装飾硝子加工から始まり現在の光学部品製造まで 一世紀半以上の歴史
1869年の創業以来、150年以上にわたってレンズを製造してきた河野光学レンズ。現在は内視鏡や眼科医向け医療機器などの医療分野とともに、生産ラインの監視カメラなどの産業分野に製品を提供している。
同社が得意とするのは多品種・少量生産の製品づくり。大量生産が必要となる身近な製品は対象とせず、分野を絞って、高品質な光学レンズを提供していく方針を掲げている。
この他、近年では、半導体製造装置や飛行場の誘導ライト、コロナ禍を受けてPCR検査装置にも採用されるなど、同社の光学レンズは縁の下の力持ちとして、社会の様々な場所で利用されている。
また、一般的に光学レンズは複数の工程を数社で分業して製造することが多いが、同社は素材の仕入れから切断、成型、研磨、組立まで社内一貫体制で生産に取り組んでいるという。
「工場の同じ敷地内で製造しているため、工程間の移動に無駄な時間がかからず、納品まで非常にスピーディーであることが当社の強みとなっています」(上田社長)
高品質なものづくりを行っている点も同社の強みの一つ。2006年よりTQM(総合的品質管理:Total Quality Management)活動を社員全員参加で展開し、品質向上に向けて取り組んできた。2020年には日本科学技術連盟の「日本品質奨励賞 TQM奨励賞」を受賞、2022年には文部科学大臣表彰の「創意工夫功労者賞」を受賞するなど、品質向上に対する姿勢が高く評価されている。
さらに、現在同社が独自に力を入れているのが「KOL(Kohno Optical Lens)未来に向けて」活動。長期的な視点を持って全員でより良い職場を実現していこうという取組となっている。
より良い職場にするための設備や社内環境、作業の効率化などに関する具体的なアイデアを社員から募ったところ、社員数とほぼ同数の149件の提案が寄せられたという。
提案は実際の設備投資に反映されており「工場の新たな製造設備の導入や、照明機器のLED化などを行いました」と上田社長。また身の回りの様々な改善につながる提案も評価し、作業の効率化や職場の整理整頓などの結果に結び付いた提案に対しては報奨金も支払われている。
こうした仕組みが社員のモチベーションを上げ、さらなる改善に挑戦しようとする姿勢を生み出している。


ベテランから若手へ。技術継承を使命に70代社員も活躍中
同社の人材育成は、OJTでじっくりと時間をかけることが基本と話すのは、採用業務にも携わる入社29年目、総務課の向井課長。
「入社以来総務の仕事をしていますが、工場見学の研修にも参加し、製品への理解度を高めることができました。当社の育成ポリシーは、ベテランから中堅社員へ、そして若手へと、長い時間をかけて着実にスキルを引き継いでいくことです」と話す。
同社には、現在も70代で活躍中の社員がいるという。そうしたベテラン社員と若手が一緒に働くことで、技術や知識を共有できる。
また、インストラクター制度という同社独自の制度もある。各種講習会には本人が希望すれば会社の費用負担で参加できるが、受講後は受講者自身がインストラクターとなって社内に学んだ内容をフィードバックすることになっている。こうした取組が、社員全体のスキルアップへとつながっているという。

社員の健康に配慮し パンの提供や広報誌を発行
ゆとりある働き方が、社風としてしっかり根付いている同社。働く環境について入社18年目、経理課の照井係長は、「有給休暇が取りやすいです。また、残業もほとんどないので、帰宅後もしっかり休めます。入社時から、この環境は変わっていません」と話す。
さらに、健康経営にも力を入れ、2022年には健康保険組合連合会東京連合会より健康優良企業「銀の認定」を取得。例えば、朝食用に会社でパンを用意して自由に食べられるようにしたり、「心の相談窓口」を設け、心の健康に配慮する体制を整えたりと、きめ細かな取組を行っている。また、健康管理への意識を高めてもらおうと、ストレッチ方法や体に良い料理レシピを掲載した社内向け広報誌も毎月発行している。

社長からのメッセージ
バイタリティーにあふれた方を求めています。本社も工場も、先輩社員がしっかりと指導しますので、安心してください。

読者からひとこと
長い歴史が支える確かな技術 150年を超える歴史がある中で、多品種・少量生産で、品質にこだわったレンズを製造している点に魅力を感じました。また、インストラクター制度を活用することで、会社の費用負担のもと、自身も周囲の社員も学びを深められると思いました。

●第32号 (2023年2月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。