適材適所で職員の個性とスキルを生かし、障害者と健常者が支え合う支援サービスを
<3つの特徴>
●事業内容:障害者に向けた幅広い支援事業を展開
●育成制度:適性を見極めた配属と研修制度で着実に成長
●働く環境:職員の状況に合わせて柔軟に休暇取得可能
共生社会の実現を目指し 障害者と健常者が共に職員として働く
社会福祉法人として、約20年にわたり八王子エリアの障害福祉サービス事業に取り組んできたもくば会。支援の対象となるのは精神・知的・身体の障害で、年齢層は児童から高齢者まで幅広く、利用者や社会のニーズに応じて事業内容を拡大してきた。
具体的には、施設入所支援、短期入所、共同生活援助、日中一時支援、就労継続支援B型、生活介護、放課後等デイサービスなどのサービスを八王子市内の13の事業所で展開している。
このような幅広い障害福祉サービスを展開できる理由の一つとして、障害を持つ当事者が理事や管理者、職員として働いていることが挙げられる。利用者にとって必要な支援を、当事者として深く理解し提供できることが、同法人の大きな特徴。前身となる無認可施設の立ち上げ時から、支援者と障害者が一緒に支え合うことを大切にしてきたと小玉理事長は語る。
「当法人は、『ともに生き、ともに創る。』という理念を掲げています。障害福祉サービスを利用する側、提供する側が同様に喜びや感謝の気持ちを感じながら、互いに成長し合い暮らせる生活を共に作っていく。私も障害を持つ当事者としてこれまでたくさんの人と支え合ってきました」
同法人は「はざまのない支援」という考え方を大切にしている。
「支援を必要としていても制度の対象ではない人たちが、世の中には大勢います。そんな生活に困っている全ての人を支援していく姿勢が、今後の我々に求められています」(小玉理事長)
必要とされるサービスを見極めるためには、障害者だけでなく、高齢者、ひとり親家庭など、様々な人に目を向けていく必要がある。あらゆる人が必要な支援を受けられることで共生社会が実現できると考える同法人では、今後、障害福祉サービスと介護保険サービスの共存も目指していくという。施設用地などのハード面についても準備をしつつあり、サービスというソフト面の向上とともに着実に次のステップに進んでいる。

2週間の体験入職制度や2カ月の事業所研修で、自分の適性を見極める
同法人では求職者がマッチングを図れるようにと、希望者には2週間の体験入職の機会を設けている。
また、新卒入職した職員は、まず法人理念やビジネスマナー、介護研修などを学び、さらに約2カ月間かけて1週間ずつ事業所を回り現場研修に参加する。この期間で適性にあった事業所を見極め、本人の希望も考慮して配属が決定されるという。
法人本部で採用や育成にも関わっている入職10年目の小松﨑事務局長は、「配属後に様々な理由で適応が難しかった場合は、相談の上で異動などに対応することもあります」と話す。
さらに、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格取得では、合格時に10万円までの補助金を支給。また、幅広い事業展開の同法人では、介護や障害に関する多様なスキルが必要とされるため、積極的な外部研修への参加も推奨している。職務に必要なものであれば、参加費用は全て同法人が負担している。
「私も未経験でこの業界に入り、働きながらホームヘルパー2級(現介護職員初任者研修)や社会福祉士の資格を取得してきました」(小松﨑事務局長)

若手も休暇を取りやすく 事業所間の交流も積極的に推進
シフト勤務が中心となる同法人では、職員が余裕を持って働けるよう休暇を取りやすい工夫をしている。シフト決定前には、必ず休みたい日を指定できるほか、常勤職員は年に3日間のリフレッシュ休暇を取得することができる。
また、産前産後休業・育児休業を取得し復職する女性職員や約2週間の育児休業を取得した男性職員もいるという。
「今は、技術を磨き先輩たちのように活躍できるように努力することで精一杯ですが、休みも取りやすく、将来ライフステージが変わっても安心して働き続けられると感じています」(入職2年目、ウイングス勤務の岩垣さん)
さらに、同法人では別々の事業所で働く職員間の交流を図るため「交流促進ボランティア部会」を設置。オンラインで定期的に交流する機会を設け、日々の悩みから趣味の話まで何でも話せる場所にもなっている。

当法人の自己PR
各事業所で研修を受ける中で「ここで働きたい」と感じた生活介護事業所ウイングスに希望を出し、実際に配属してもらえたのがとても嬉しかったです。先輩職員たちも優しくサポートしてくれ、安心して働けています。当法人は様々な事業フィールドがありますので、もし今後やりたいことが変化しても選択肢が幅広いことも魅力です。(岩垣さん)
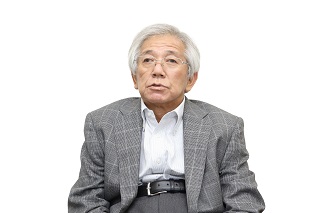

●第26号 (2021年10月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。


