「子どものしあわせ」を第一に考えた保育と、やりたいことを実現できる環境で成長
<カイシャの特徴>
●事業内容:子どもの気持ちを大切にした保育
●育成制度:OJTでフィードバックをもらえる
●働く環境:1時間単位で取得可能な有給休暇
●仕事のやりがい:子どもとやりたいことを実現する
子どもが「しあわせ」に安心して成長できる環境でチーム保育の充実を図る
「子どものしあわせ」を保育理念に掲げる愛光学舎の歴史は古く、開園は1949年。現在、立川・八王子エリアに認可保育所5施設、分園4施設を運営する多摩地域に根差した保育園である。
全ての園で、異年齢保育(0・1・2歳児クラス、3・4・5歳児クラス)を実施しており、年齢の異なる子ども同士が関わることで伸び伸び成長していくことを目指している。
「園によって子どもの人数が25人から150人と規模に違いがあります。大勢の子どもたちとにぎやかな環境で保育をしたいタイプ、こじんまりした環境でゆったりと保育に取り組みたいタイプなど、働く職員の希望にも応えられる環境が整っています。もちろん保育理念や保育の進め方はいずれの園でも変わりはありません」(佐野理事長)
また、子どもの幸せを第一に考える同法人では、職員の幸せも大切にしており、福利厚生制度や人材育成制度を充実させている。今後に向けて取り組んでいるのが、勤務体制の整備と話す佐野理事長。
「現在は、早番・中番・遅番の3シフト制を導入しています。ただ、不規則な勤務は職員の負担になることもあります。そこで、早番・遅番に特化したスタッフをサポートに入れ、職員は基本的に中番で勤務できるようになるよう計画しています。この体制の構築に向けて、様々な準備をスタートさせたところです」(佐野理事長)
職員が体力的にも気持ち的にも余裕を持ち、子どもと向き合う時間が自然と増えることで、より良い保育の実現を目指している。

新入職員研修やOJT研修、フィードバックシートでしっかりと成長を支援
同法人では、新卒内定者に向けた有償の入職前オリエンテーションを実施して、4月にスムーズな入職ができるようサポートしている。また、本人の希望する時期からアルバイト勤務をすることも可能になっている。
「私は3月からアルバイトをしました。先輩たちが丁寧に教えてくださり、入職する4月が楽しみになりました」(入職3年目、3・4・5歳児クラス担任の木村さん)
入職後は5月まで新入職員研修に参加し、その後はOJTで仕事を覚えていく。毎日の業務報告や相談事項については「フィードバックシート」に記入し、先輩や上司に提出。アドバイスをもらうことができるという。
「フィードバックシートに記入していくことで、自分の日々の行動を冷静に整理できるので、成長につながっていることを実感できます」(木村さん)
さらに、外部講師を招いて幼児教育に関する研修を実施しているほか、法人が必要と判断した資格取得費用の支援など、様々な面から職員のキャリア形成を支援している。

1時間単位でも取得できる有給休暇や少ない残業。働く環境の整備に注力
子育てをしながら働き続ける職員が多いという同法人。残業も少なく、有給休暇は年に2日分まで1時間単位でも取得でき、取得率は90%以上。また、入職1年目から夏季休暇を連続8日間取得することが可能になっている。
「プライベートとのバランスが取りやすい職場です。育児休業から復帰する先輩職員も多く、皆が待っているよという温かい雰囲気があります」(入職9年目、3・4・5歳児クラス担任、クラスリーダーの道祖土(さいど)さん)
子どもたちや職員同士の交流だけでなく、保護者とのコミュニケーションも重視する同法人では、管理職の職員が中心となり保護者向け冊子「すまいるかーど」を月2回発行している。10年以上発行し続けているこの冊子は、保育スキルの向上にも役立っている。
「最近では野菜を育てるための土づくりから行い、食育の事例として掲載しました。職員や子どもたちと一緒になって進めましたが、勉強になりとても良い経験でした」(道祖土さん)

子どもが喜ぶこと、一緒にやりたいことを考えて実現していく
職員の自主性を尊重し、子どもと一緒にやりたいことを可能な限り実現していく方針だと話す佐野理事長。
「『子どもと一緒に山に登りたい』『新幹線を見に行きたい』など様々な希望を実現してきました。先日は5歳児が高尾山に登ってきました。子どもが楽しいことは何かを考え、実現させていく。それが私たちのやりがいであり、職員の成長にもつながっています」

理事長からのメッセージ
保育士だけでなく、栄養士、看護師も勤務しています。子どもの幸せを考え、チームで子どもを育み、共に成長していける保育園を目指しています。

このカイシャが10秒でわかるムービー
ムービーはこちら
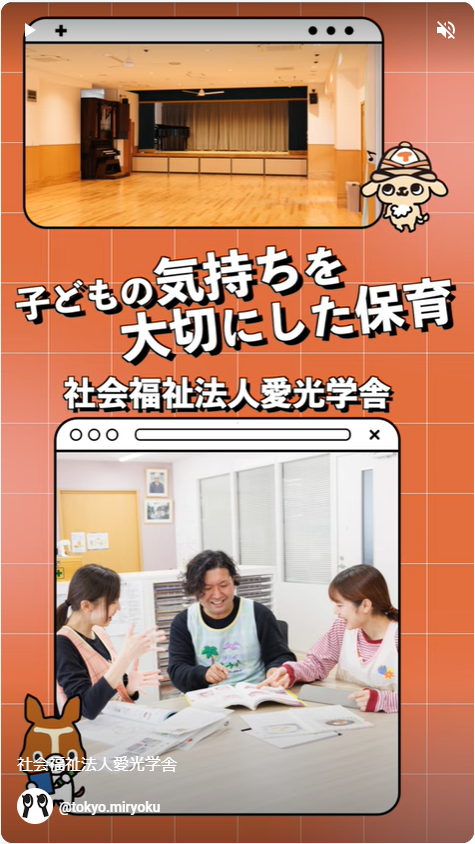
●第33号 (2023年6月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。


