独自のシステム移行サービスで大手を支援。社員同士の交流で若手が自然と成長できる
<カイシャの特徴>
●事業内容:システムの移行支援と受託開発
●仕事のやりがい:大手顧客と直接やり取りできる
●育成制度:新人1人を複数の先輩がサポート
●働く環境:社内交流が生む風通しの良い社内
受託開発とともに、大手企業の基幹システム移行を自社サービスで支援
かつて主流だった大型ホストコンピューターを使うシステムから、より柔軟性に富むPCを活用したシステムへの移行には、プログラミング言語の変換が欠かせない。その変換を自動で行うサービス「VENUS」を2002年から提供し始めたことで、ジェイ・クリエイションは独自の地位を築き成長を遂げてきた。
「機能や堅牢性(けんろうせい)に優れる一方、システムの構築や維持に費用のかかるホストコンピューターを利用してきたのは、ほとんどが大企業です。そのため、当社の取引先は皆さんが知っているような名だたる企業が中心です」
そう上山社長が話すように、大手企業から直接受注する元請案件の比率が受注全体の約90%を占めるという。
VENUSという独自の技術で顧客基盤を築いてきた同社だが、高い技術力をもとにした受託開発も得意とし、自社内での企業向けシステム開発が案件の7割を占めている。中でも得意とするのが、金融業界のキャッシュレス決済関連や、ビルの省エネなどを見える化する脱炭素関連のシステムだという。
同社は設立時から「研究開発型企業」として、一歩一歩業績を拡大してきた。そして2019年、上山社長は「これからは第3創業期と位置付け、本格的にメーカーを目指す」という新たな目標を打ち出した。
「自分たちで作りたいものを作る方が楽しいですし、やりがいも大きいです。下請を脱した第2創業期で元請としての実績を重ねてきたので、いよいよ本来の目標に向かいたいと考えています」
コロナ禍により一時ストップしていたが、2023年には社内横断で公募型の研究開発チームを立ち上げた。若手中心のこのチームで自由に意見を交わしてVENUSに次ぐ独自製品を生み出し、研究開発型のITメーカーを目指そうとしている。

大手顧客と直接やり取りし プロジェクトの進行を管理する責任とやりがい
大手企業から直接依頼される案件が多いため、同社エンジニアは最初から開発に関わることができるという。プロジェクトマネジメントなど重要な役割を担える点も、やりがいにつながるという。
「良いものを作ろうとお客様と直接話し、一体感を持って開発できるのは大きなやりがいになっています」(入社10年目、クレジットカード関連システムの開発リーダーを勤める男性社員)
また、入社5年目、不動産関連システムの開発サブリーダーの女性社員は、IT未経験で入社。エンジニアの仕事の面白さは入社してから知ったと話す。
「自分が作ったものが思い通りに動くことにまず感動しました。何より、当社のエンジニアはコードを書くだけでなく、プロジェクトマネジメントという重要な役割を担えるところに、とてもやりがいを感じています」

複数の先輩社員が新人をサポート。2年目以降も きめ細かな育成環境を用意
同社では、新人がより早く成長することを目標にしている。入社後3カ月間の外部研修でJava言語の基礎知識を学んだ後、1年目は配属先でのOJTが中心となる。この期間は、新人1人につき2~3人の育成担当の先輩社員が付く。
「担当の先輩社員が1人だけだと、新人の相談に常に対応できるとは限りません。それでは新人の成長の妨げになると考え、年次の近い複数名の社員をOJT担当にしています」(上山社長)
2年目以降も知識や技術レベルに応じた研修カリキュラムを整えており、プロジェクトリーダーを育成する上で必要な知識を習得する研修もある。入社5~6年目には5人程度のメンバーを束ねるサブリーダーになり、10年目には一定規模の案件のプロジェクトリーダーを担えるようなスキルを身に付けることを目指している。

日々の社内交流が作る風通しの良い社風。時間有休も利用可能
受託開発案件が中心の同社は、自社内で勤務する社員が多く、積極的なコミュニケーションが交わされる風通しの良い社風という。また社内交流イベントも開催され、働く社員を支える家族を大切にしたいという上山社長の方針で、忘年会やバーベキューには社員の家族も参加できる。
さらに、子どもが誕生すると手当が支給されて、一人目は毎月1万円、二人目以降は金額が増額。子どもが高校を卒業するまで続く。
加えて、有給休暇の取得もしやすく、1時間単位で取得できる時間有給休暇制度も導入している。
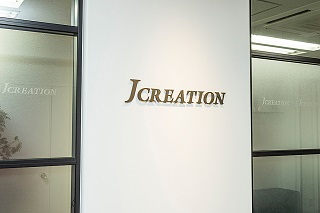
社長からのメッセージ
当社では成長を後押しする育成制度や、チャレンジ精神が発揮できる機会を手厚く用意しています。思いやりとチームワークで一緒に成長しましょう!

このカイシャが10秒でわかるムービー
ムービーはこちら
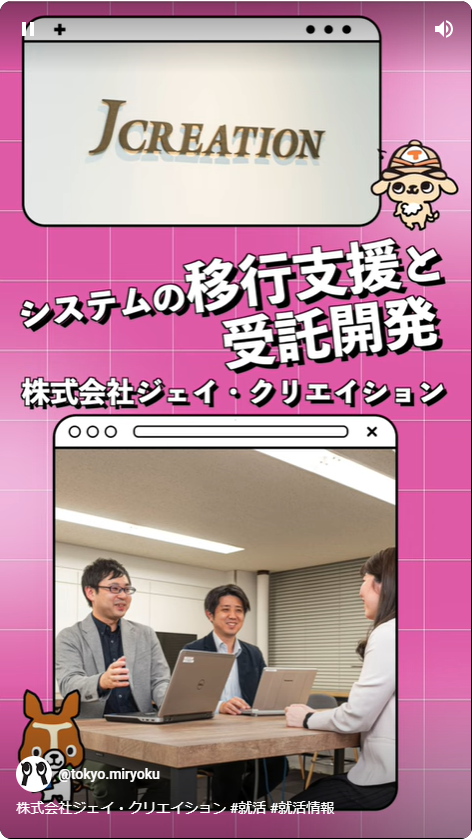
●第36号 (2024年3月発行)掲載 ※掲載内容は発行日時点のものです。


